中小企業の経営者のみなさまに、『社会保険の加入の義務からメリットを生かす経営戦略』として、『障害年金制度を活用した福利厚生制度の導入』について、ご提案させていただきます。
ここ数年の間に、以前は加入を必要としなかったパートやアルバイトの従業員に対し、厚生年金保険への加入が義務づけられて参りました。
年々、段階的に、強制加入の要件である従業員規模が小さくなっていることを、経営者の皆様は既にご存知かと思います。
これまでは必要で無かった事業主負担の経費の発生と、配偶者の扶養になっている従業員からの不満への対応等、経営者の皆様にはご苦労されていることを耳にしております。
ただ、デメリットのみに目を向けますと、企業並びに従業員には負担としか目に映りません。
なかには「制度の改悪だ!」と思われている方もいるのではないでしょうか?
けれども、物事には全て両面があり、長所短所が存在します。
デメリットがあれば、メリットもあるはずです。
ところが、「加入義務」から「経営側及び従業員側に対する経費負担等」というデメリットのみが伝わり、その代わりに「制度の仕組みによる受けられるべきメリットの内容ががきちんと伝わっていない」、私はそう感じました。
強制加入とはいえ、せっかく加入した厚生年金の仕組みを勉強会等できちんと従業員へ周知し、企業として従業員の待遇改善に精一杯の努力をしていることを、アピールすべきではないでしょうか?
きちんと説明をして従業員の理解を求めることで、大きな費用をかけずに経営側とその従業員がお互いが歩み寄れるのだと、私は思います。
費用負担の必要のない経営戦略
私は、今すでに企業の中に存在する制度を活用した一つとして、このことをご提案させていただきます。

公的な年金制度として、国民年金と厚生年金の制度があります。
このそれぞれの制度には、病気やけがにより仕事や生活などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金の仕組みがあります。
それが、障害年金の仕組みです。
普段、既に経営者及び従業員の皆様が負担している掛け金の他に、負担が必要となることはありません。
ところが、このことをご存知でない企業の経営者の皆様が多いことを知りました。
私は大変驚きました。

私はある企業に、障害年金申請代行業務のことでちょっとお尋ねしたことがありました。
すると、その企業の経営者の方からこう質問されました。
「その障害年金というものの、掛金は事業主が払うのですか?それとも従業員が払うのですか?」
ひょんなことから私は、この企業に詳しいご説明をすることになり、県外にあるその企業の本部へ行くことになったのです。
その際に、私はある疑問を感じました。
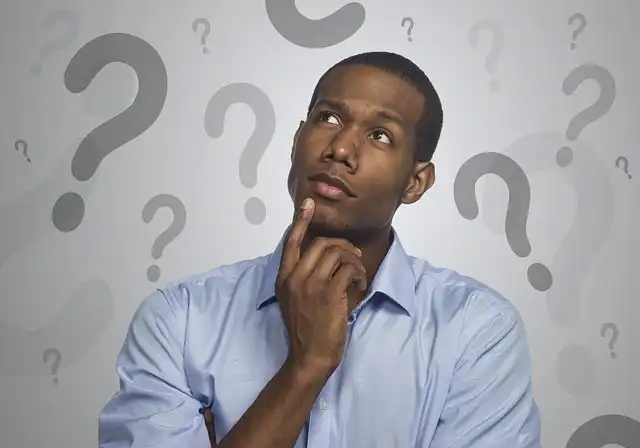
「負担となるデメリットのみが先行していて、メリットの方が全く周知できていないのではないのだろうか?」
その企業もかなりの店舗数を抱える販売店で、社労士も顧問としているようでした。
が、そのような状況からみて、厚生年金に加入した際に受けられるメリットについて、説明が行き届いていない様子が伺えました。
これでは負担しか目に入らず、労使双方から「制度の改悪」だと思われても無理のないことだと、私は思いました。
「社労士としてこれは何とかできないものか?」
このとき、私はそう考えたのです。

前述の企業へ説明に行く前にその企業の経営者と打合せして、私は次のことをご提案いたしました。
・企業の経営に携わる皆様に、まず「障害年金の制度について」理解をしていただくこと。
・次に、障害年金の制度について、社会保険労務士として私が従業員向けに勉強会で説明を行う等により、周知徹底を図ること。
・もしも、今後、障害年金のことで従業員から相談があった際には、私が企業の窓口として従業員への対応を行うこと。
・企業として、これらに付随するサービスを加えるなどして、企業独自の福利厚生事業の一環として行うこと。
・これからは春闘の時期でもあり、その賃金アップの話と合わせて、労働組合へ福利厚生事業として提示し、従業員の待遇改善について十分配慮していることを説明し、企業としての姿勢をご理解いただけるよう、話を進めていくこと。
・結果として、従業員の信頼を得ることができれば、従業員のモチベーションアップにもなり、また企業のイメージアップにもつながり、企業としてさらなる発展を目指す上での原動力ともなり得るものであること。

世の中は春闘のまっただ中であり、今年10月には昨年以上の最低賃金の引き上げもあると取り沙汰されています。
大企業のみならず、中小企業にあっても、賃上げの問題は避けては通ることのできないものとなりました。
それなら、デメリットと思われることと表裏一体となるメリットにも目を向け、従業員へきちんと説明をし、また企業独自の手段を講じることで、総合的な従業員の待遇改善を図るべく、検討すべきではありませんか?
そうして、従業員と歩み寄り従業員にも企業の中にある問題の存在を理解していただき、共に解決する手段を考えながら前進をしていく。
社員全員に『企業の問題=従業員の問題』と考えていただき、社内に『企業の発展=従業員の待遇の向上』という図式を定着させてしまうことで、経営者と従業員が『心を一にする』ことができると私は考えますが、いかがでしょうか?
『心を一にする』ことができれば、企業の未来のビジョンを共有することもでき、企業にとっては大きな推進力となり得るはずだと私は思います。

私は、このことで企業の経営者の皆様がきちんと従業員と向き合い、お話しをされる機会を持つこととなり、お互いに歩み寄るきっかけとなればと存じます。
『企業=チーム』であり、『企業の発展=従業員の幸せ』となってこそ、大きな推進力を得られるのだと、私は信じています。

このような考えで、私は企業の経営者の皆様へ、障害年金制度を活用した福利厚生事業の導入を、ご提案させていただきます。
既存の制度の活用により、全社が一丸となることができれば、今後にどんな問題が生じても恐れること無く、前に進めるのではないでしょうか?
先行きが不透明な現状を考えれば、『団結力=チームワーク』こそが一番大切なものだと私は思います。
その一例として、以上のことをご提案させていただきました。

このご提案を説明するにあたり、報酬をいただくことはありません。
もし、遠方であれば、従業員の皆様に対する学習会等への出席のために要する交通費等の実費程度をお考えいただければ幸いです。
御社の発展が社会のためとなり、またそのことが周り巡って、きっと私を含める社会の全ての人にも恩恵をもたらすことができると信じています。


「One for All, All for One(ワン フォー オール オール フォー ワン)」
ラグビーで有名な言葉です。
ドラマでもよく耳にしました。
本来の意味は、「1人はみんなのために、みんなは1つの目標のために」ということのようです。
1600年代のヨーロッパでの出来事で初めて歴史に登場しました。
「チームの一人一人はチームの勝利のために、お互いがそれぞれできることを全力を尽くす」
そうして「チーム一丸となって勝利を目指す」
このことは、企業経営にもつながるものだと私は思います。
・企業の目的、目標は何か?何を目指しているのか?
・従業員一人一人のそれぞれの役割とは何か?
・従業員がお互いに考え方、意思を共有できているか?
・従業員のそれぞれが個々の従業員を尊重し、尊敬の念を持って接しているか?
・組織、個々の従業員の間に強い信頼関係が存在しているか?
「チームとしての目標の明確化」をし、また目標達成に向けて「人を育てること」。
そして「チームのレベルの向上、開発」をして、「チームの推進力をUP」することで「目標達成」へ。
私は、経営者の皆様と従業員の方々も、「企業」という同じチームの一員として、お互いに尊重しあえる関係であればと思います。

『One for all All for one』~『一人はみんなのために、みんなは一つの目標のために』~
私が大好きな言葉の一つです。
私は、昭和59年に高校を卒業してすぐに徳島県庁に入職しました。
私が県庁へ入ってずっと夢見てきたのは、このサイトにあるラグビーの写真のように、みんなで団結して目標を達成することでした。
ただ、それだけでした。
出世とかお金とかそういうものではありません。
私は幼少の頃、児童養護施設で過ごした日々もあり、親元に引き取られてからも虐待のようなことが続いていました。
やっと自分の家庭を持つことができてと思ったときに、うつ病となりました。
数年間の療養生活を送り、離婚し、ローンの支払いを終えてマイホームを明け渡して、仕方なく親元に戻ってしばししてから、その上に難病をも患うこととなりました。
難病を患った際に、私に言った、「長男は家の犠牲になるために生まれてきた」と語った母の言葉通りの、今思えば、私の一生はその言葉そのものでした。
ところで、長い間の難病とのことで「風邪でも危ない」と言われてきた私でしたが、社労士として開業したのは、ある覚悟をしたからでした。
知人である、ある地元の地方議員が有志と共に自費でもって、コロナウイルスの騒動の中、食べるものにも困窮している学生のために、月に2回、定期的にチラシを配布し、大学の近所で食べ物を分けてあげていたことを知って、私は驚きました。
コロナウイルスの騒動が起こり、「感染するかもしれない」と不安が日々増していく日々を送りながら、そのことが頭から離れませんでした。
すいぶんと悩んで出た答えは、
「どうせなら自分がやりたいことをやりきってから。悔いの無いように残りの人生を生き抜きたい!」
ということでした。
運命とかそういうことに翻弄されたようにして、自分の人生が終わることに私はどうしても納得ができなかったのです。
そうして、今、私は社会保険労務士として開業し、ここに居ます。
私も、県庁は辞めましたが、最後にもう一働きしたかったからです。
あの地方議員の姿に私の心は振り動かされたのです。
家庭が駄目でも、学歴が無くても、お金が無くても、出世ができなくても、ただ同僚とみんなで一緒に一つの目標の達成のために、人生をかけたかった!
お金よりも、地位や名誉よりももっと大切なもの、それは人の心の中にこそあるのだと、私は思います。
これからまだ先の長い、若い方たちに、そのことを教えてあげられる世の中であって欲しいし、また企業であって欲しい。
そうしないでこれから先に、老弱関係なく、「あのときこうすれば」と後で悔いが残らないように人生を送ることができるでしょうか?
「心の中にいる熱い心を持った自分の姿」を感じてもらえる、社会であって欲しいと私は願います。
令和5年5月 楠 昇